JETRO(日本貿易振興機構)の特集で海外事業部の取り組みが紹介されました2025.12.29/Uganda Project, NEWS
ウズベキスタンで浄化槽システム導入に取り組むテラオライテック
テラオライテックは1966年創業の企業で、設備工事や電気工事などの事業に取り組んでいる。海外ではカンボジアやブータンで上下水インフラの整備に取り組んできた。現在もウズベキスタンとウガンダで浄化槽の導入に向けた実証を進める。同社のグローバルサウスでの取り組みの現状と課題について、ウズベキスタンを中心に、同社海外事業部田嶋健氏(ウズベキスタン担当)と廣瀬遥氏(ウガンダ担当)にそれぞれ聞いた(取材日:2025年11月5日)。
二重内陸国のウズベキスタンでのニーズに注目


ウガンダでは国営企業に出向者を派遣


詳しくはJETRO(日本貿易振興機構)サイトをご覧ください。
JETRO(日本貿易振興機構)サイトを見る >
Uganda Project 第11章【Johkasou技術紹介セミナー開催報告】2025.11.27/Uganda Project, NEWS
2025年11月14日、カンパラ市のNWSC International Resource Center(IREC)にて、日本の分散型汚水処理技術である浄化槽に関するステークホルダーセミナーを開催いたしました。
本セミナーは弊社主催のセミナーで、KCCA(カンパラ首都省庁)とマケレレ大学協力のもと、
J-Partnership事業の一環として実施されたものです。政府機関、開発パートナー、研究者、民間企業など、ウガンダにおける水環境分野の主要ステークホルダーが多数参加し、国内外の重要機関と技術的議論を行う貴重な機会となりました。

セミナー準備にあたっては、会場確保、プログラム作成、講演者との調整、バナー・パンフレット等の広報物制作、費用見積り、招待状配布、そして当日の進行まで、多岐にわたる業務を担当いたしました。ウガンダでは想定外の事態が生じることも多く、本セミナー準備においても直前の会場調整や印刷物の遅延など、複数のイレギュラーが発生しましたが、関係者の協力のもと無事に当日を迎えることができました。


当日は、会場参加67名、オンライン参加33名の計100名が参加され、当初の想定を大きく上回る規模となりました。世界銀行、アフリカ開発銀行、水環境省、保健省、NWSC(国家上下水道局)をはじめとする重要機関の参加者が揃い、各講演後には活発な質疑応答が行われました。また、国営新聞およびテレビ・ラジオなど複数のメディアに取り上げられ、浄化槽技術に対する社会的関心の高さを改めて実感する結果となりました。国営紙に自身の名前が掲載されたことは、ウガンダでの活動が確かに形になっていることを感じる一つの節目ともなりました。



今回、企画立案から運営まで一連の業務を担当する中で、大学で学んだイベントマネジメントの知識や経験が、思いがけず現場で大きな助けとなりました。業務の中で“基礎力”が活きる瞬間があり、小さな積み重ねの重要性を実感しました。
また、日本から1週間ほど上司が現場を視察し、運営状況を共有する機会にも恵まれ、さまざまなアドバイスをいただくことができました。さらに、日本側のメンバーがオンラインでセミナーを見守ってくださり、離れていてもチームとして支えていただいている心強さを感じました。


Uganda Project 第10章【浄化槽設置候補地の現地視察を開始】2025.11.27/Uganda Project, NEWS
経済産業省の支援制度「J-Partnership」による補助金事業 https://j-partnership.go.jp/として、浄化槽のテスト設置に向けた候補地選定が、本格的に動き出しました。
本事業では、カンパラ市を中心に、ウガンダ各地で浄化槽導入の可能性を調査することが目的です。7月の事業開始以降、KCCA(カンパラ首都庁)およびマケレレ大学と連携し、合計14か所の現地視察を実施しました。
各施設では、排水量、敷地条件、既存の処理方式と問題、管理体制などの観点から評価を行いました。視察結果をもとに評価シートを作成し、複数回の協議を経て、最終的に5か所をテスト設置の重点候補地として選定しました。現在は、各候補地で水質検査を行っており、結果を待つ段階です。

選定された5つの重点候補地
カンサンガ小学校(Kansanga Primary School)
低地に位置し、過去にバイオトイレや湧水処理の実証が行われたことのある施設です。学校側の理解も得られ、管理体制が確立していることから、学校施設の代表例として選定しました。
ルビリ中等学校(Lubiri Secondary School)
大規模で管理体制が整っており、複数建屋を接続可能な構造を持っています。デモンストレーションに適した環境です。
ナチインギ・ホステル(Nakiyingi Hostel)
下水道未整備地域にある学生寮で、敷地が限られています。小スペースで設置可能な日本式浄化槽の特長を活かせるため、小型モデルの実証候補地として選びました。
ルジラ市場(Luzira Market)
既存の浸透槽(ソークピット)が機能せず、生活排水が周辺住宅地へ流出しています。衛生環境への影響が大きく、水環境省の施設にも近いため、効果検証に適しています。
マキンデ地区のアパート(24戸)
近年増加しているアパート型住宅の代表例です。既存の浸透槽が機能しておらず、排水が側溝へ直接流出しています。住宅向けモデルの検証に適しています。

選定された5施設は、用途や地形、排水特性の異なる代表的なケースを網羅しているので、将来的な浄化槽設置モデルの比較検討に有効なサンプルとなります。また、現在行っている水質検査の結果は、浄化槽単独で排水基準を満たせるか、あるいは追加対策が必要かを判断する上で重要な根拠となります。こうして、浄化槽設置候補地の選定プロセスをおこない、今後の最終候補地決定に向けた準備を進めています。
Uganda Project 第11章【Johkasou技術紹介セミナー開催報告】を見る >
Uganda Project第9章【TICAD公式パートナー事業イベント登壇】2025.09.11/Uganda Project, NEWS
2025年8月3日、TICAD9公式パートナー事業「Sport for Tomorrow × Africa Action Day 2025」の公式イベントに登壇しました。本イベントは「ビジネス・国際協力・スポーツ・ユース」をテーマに、官民・世代・分野を越えてアフリカとの未来を語り合う特別企画です。私はその中で「ユース」セッションに参加し、アフリカと関わるZ世代の一人として、自身のこれまでの歩みや現在の活動についてお話ししました。

TICAD9とは
TICAD9(ティカッドナイン)とは、**第9回アフリカ開発会議(Tokyo International Conference on African Development)**の略で、アフリカの持続的な成長と発展を支援する日本が主導する国際会議です。1993年から国連、国連開発計画(UNDP)、世界銀行、アフリカ連合委員会(AUC)と共同で開催されており、2025年8月には横浜で開催されました。会議では、アフリカ自身のオーナーシップを尊重しつつ、日本とアフリカが「共創」を通じて経済協力やビジネス拡大を推進する方向性が示されました。
詳しくみる >(外務省サイトへ飛びます)
公式イベントでのセッション内容
登壇では、「なぜアフリカだったのか」「どのようにキャリアを選んだのか」「今後どこを目指すのか」といったテーマで、自分の経験を踏まえてお話ししました。
特に、現地で働くことを通じて学んだ挑戦の大きさと成長の機会について、他の登壇者の皆さんと一緒に意見を共有しました。
また、参加者とのQ&Aでは「アフリカに関心はあるけれど何から始めればいいか」という学生や若手社会人からの質問が多く寄せられました。
私自身の経験を踏まえて、情報発信やインターンシップ、そして現地での体験の重要性を具体的にお伝えしました。

イベントを通じて感じたこと
今回のセッションには、ルワンダで起業した同世代の経営者や、JICA協力隊として活動した経験を持つ若手、アフリカ起業プログラムの代表を務める研究者など、さまざまなバックグラウンドを持つ登壇者が参加していました。
それぞれ異なる形でアフリカに関わっている姿を見て、「アフリカとの関わり方に正解は一つではない」ということを強く感じましたし、私自身もその一人として、現地で得られた学びや挑戦を発信し続けたいと思いました。
このイベントに登壇したことで、自分の活動を改めて言語化し、次世代へのメッセージとして伝える機会をいただきました。
今後もウガンダ駐在での業務を通じて、日本の技術を活かした持続可能な水環境の構築を進めると同時に、同世代や次の世代に向けて「アフリカと関わる一歩」を示していける存在でありたいと思います。
Uganda Project 第10章【浄化槽設置候補地の現地視察を開始】を見る >
Uganda Project第8章【ウガンダでの暮らし〜日常に息づく発見と学び〜】2025.08.20/Uganda Project, NEWS
ウガンダでの暮らしは、仕事だけでなく、日々の生活そのものが新鮮な驚きと学びの連続です。
現在滞在しているウガンダの首都カンパラはアフリカの中でも比較的発展しており、ショッピングモールやスーパーマーケットが整備されているため、日用品の調達に困ることはほとんどありません。
ただし、停電や断水は日常的に起こるため、日本とは違った生活リズムに自然と慣れていく必要があります。
ハプニング発生

ある日、住んでいるアパートの屋上で業者が配管工事を行っていると、雨水タンクの水が大量に流れ出し、部屋の天井から水がポタポタと漏れ出すハプニングが発生しました。その後、配管を修理したにもかかわらず別の場所から再び漏水が起きるなど、インフラのありがたさを身をもって実感する出来事もありました。
とはいえ、こうしたトラブルも「アフリカに来たなあ」と感じられる一コマ。少し視点を変えれば、どれも学びの機会だと楽しめています。
ただ、それを除くと現在住んでいるアパートは非常に快適で、安全面も含めて大きな問題はありません。目の前では大型のビル建設が進行中で、朝7時にはコンクリートを流す機械音が目覚まし代わりになる日々(笑)。都市の発展やインフラ整備の「動いている現場」に囲まれて生活していると、自分の仕事がこの中でどう貢献できるか、自然と考えるようになります。
ウガンダの食文化

食文化もウガンダ生活の大きな魅力です。マトケ(蒸したバナナ)やポショ(トウモロコシ粉を練った主食)、豆の煮込みや肉のシチューなど、地元ならではの料理が日常的に楽しまれています。

なかでもお気に入りは「ロレックス」。チャパティに卵と野菜を巻いたシンプルなストリートフードで、屋台で手軽に買えて、味も抜群です。
週末の楽しみ方
 週末には友達とテニスをしたり、家に遊びに行ったりしています。先日は「Rugby Africa Cup 2025」の決勝戦を観戦し、ジンバブエ対ナミビアの白熱した試合を楽しみました。ジンバブエが優勝し、2027年のラグビーワールドカップ出場権を獲得!ウガンダ代表は8カ国中7位という結果でしたが、会場の熱気と応援の盛り上がりは誰にも負けていませんでした。
週末には友達とテニスをしたり、家に遊びに行ったりしています。先日は「Rugby Africa Cup 2025」の決勝戦を観戦し、ジンバブエ対ナミビアの白熱した試合を楽しみました。ジンバブエが優勝し、2027年のラグビーワールドカップ出場権を獲得!ウガンダ代表は8カ国中7位という結果でしたが、会場の熱気と応援の盛り上がりは誰にも負けていませんでした。
 文化的な違いも楽しみのひとつです。街を歩いていると「ムズング!(外国人)」と声をかけられることは日常茶飯事。初めは戸惑いましたが、今では笑顔で応える余裕もできました。
文化的な違いも楽しみのひとつです。街を歩いていると「ムズング!(外国人)」と声をかけられることは日常茶飯事。初めは戸惑いましたが、今では笑顔で応える余裕もできました。
もともと数回の渡航経験があり、地方に滞在していたこともあるため、文化の違いも楽しみながら受け入れられています。また、ウガンダでは、双子がとても喜ばれる存在なので、私に双子の妹がいると話すと、「あなたは“Babirye(バビリエ)=姉の方」ね」と現地の方に呼ばれ、すっかりセカンドネームのようになっています(笑)。
こうした日常の交流の中で、日本に興味を持ってくれる人も多く、現地スタッフとの関係もとても良好です。
ウガンダの生活は、時に不便もありますが、それ以上に人の温かさや前向きなエネルギーに触れられる機会に恵まれています。仕事の場だけでなく、日々の暮らしの中からも多くを学び、吸収し、支えられていることを実感する毎日です。
Uganda Project第9章【TICAD公式パートナー事業イベント登壇】をみる >
Uganda Project第7章【日本の補助金制度でウガンダの衛生環境を改善】2025.08.07/Uganda Project, NEWS
今回のウガンダ駐在では、出向業務と並行して、経済産業省の支援制度「J-Partnership」による補助金事業を実施しています。
J-Partnershipについて詳しくみる >
J-Partnership補助金について
J-Partnership補助金は、経済産業省が実施する支援制度で、日本企業と海外の現地パートナーが協力して、現地の課題解決や事業展開を進めるための取り組みを支援するものです。特に、開発途上国でのビジネス展開や技術導入を促進することを目的としています。
この補助事業を通じて、弊社は「ウガンダ共和国における日本式合併処理浄化槽導入による生活排水処理改善プロジェクト」を実施しています。ウガンダの生活排水処理の現状や制度を調査し、浄化槽導入のニーズや課題を把握することで、パイロット設置や維持管理体制の構築、現地人材の育成を進め、制度化と普及を目指していきます。

2025年7月10日には、マケレレ大学教授のDr. Swaib Semiyaga氏とキックオフミーティングを行い、補助事業の内容や今後のスケジュールについて確認しました。
7月18日にはカンパラ首都省庁(KCCA)の技術チームと会議を開き、補助金事業の段階的な進行方法や、候補地の条件や評価基準について議論しました。7月下旬から8月にかけては、実際に候補地の視察を開始し、浄化槽導入に適した場所を絞り込み、評価していく予定です。

これらの取り組みを通じて、ウガンダ・カンパラにおける現状の排水処理状況や浄化槽導入のニーズ、課題を的確に把握し、持続可能な生活排水処理システムの構築に向けた基盤作りを着実に進めています。
Uganda Project第8章【ウガンダでの暮らし〜日常に息づく発見と学び〜】をみる >
Uganda Project第6章【ウガンダ駐在開始、出向先へ】2025.07.25/Uganda Project, NEWS
2025年7月、ウガンダ駐在が始まりました。

いよいよウガンダ駐在がスタートしました。
今回の駐在の目的は、現地の下水処理事情を実地で学び、日本とウガンダの将来的な技術協力に向けた基盤を築くことにあります。
当初は6月24日に日本を出発する予定でしたが、中東情勢の影響により一部空域が閉鎖されたため、出発は1日遅れの6月25日となりました。ウガンダ到着後は首都カンパラでの生活基盤を整えるとともに、関係機関との業務調整を進め、スムーズに現地での活動を開始できるよう努めました。
出向先はウガンダ国家上下水道公社

現在は、ウガンダ国家上下水道公社(National Water and Sewerage Corporation:NWSC)への出向活動が始まり、下水サービス局にて本格的な業務に取り組んでいます。
NWSCはウガンダ全土で上下水道サービスを提供する国営企業であり、特に首都カンパラでは急速な都市化に対応した下水処理体制の整備が喫緊の課題となっています。配属先である下水サービス局では、下水処理施設の運転管理や水質検査、スラッジ処理、排水規制などの業務を現場で学んでいます。
7月は、大規模下水処理場を訪問し、処理プロセスや運転管理の現場を視察したり、水質検査や微生物分析の実験にも参加したりしながら、下水処理に関する実務的な知識とスキルを習得しました。

特に印象的だったのは、「理論」だけでは解決できない現場のリアルさです。
設備の老朽化、運転条件のばらつき、水質モニタリングの精度など、日本とは異なる前提条件の中で、どのように「最適」を追い求めるか。今後の技術協力やプロジェクト提案に活かせる視点を、日々の現場から学び続けています。
水処理を通じた技術や文化の共有

活動を通して、現地の技術者やスタッフの方々から直接指導を受ける機会も多く、例えば水質検査の手法や、スラッジ処理における注意点、曝気効率の確保など、実務に基づいた学びを日々積み重ねています。NWSCで働いている方々はとても親切で、こちらの学びをサポートしてくださると同時に、日本についても深い関心を示してくれます。私が日本の下水処理や制度について説明すると、活発に質問が飛び交い、双方向の学び合いが自然に生まれていると感じます。
このように、技術や文化を共有し合える関係が築けていることは、非常に貴重な経験です。私自身、下水処理や排水処理についてはさらなる勉強が必要ではありますが、現地の方々と共に歩み、将来的に実りある技術協力につながるよう努力を続けています。
Uganda Project第7章【日本の補助金制度でウガンダの衛生環境を改善】をみる >
Uganda Project 〜起業家の挑戦〜2025.01.09/Uganda Project
水の課題を抱えるUgandaにアフリカ地域では初となる現地法人を設立を目指しています。 このプロジェクトを担当するのは2024年4月に起業家育成プロジェクトを通じて入社した廣瀬遥。
ここでは彼女のあくなき挑戦の裏側にある苦悩や楽しさ・達成感をリアルに伝えていきます。
ウガンダ挑戦記をみる >




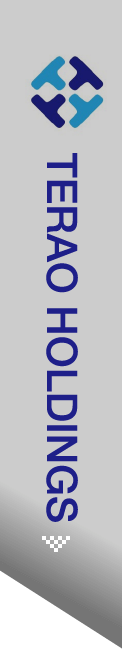

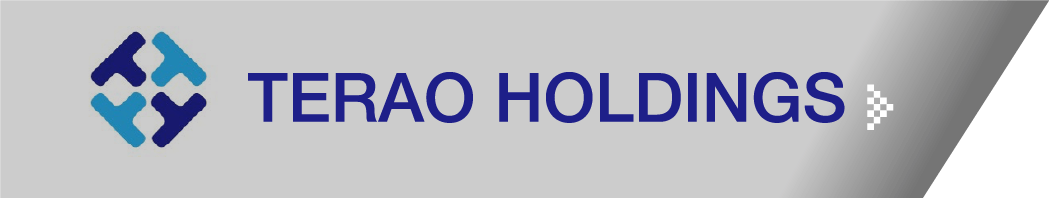















 週末には友達とテニスをしたり、家に遊びに行ったりしています。先日は「Rugby Africa Cup 2025」の決勝戦を観戦し、ジンバブエ対ナミビアの白熱した試合を楽しみました。ジンバブエが優勝し、2027年のラグビーワールドカップ出場権を獲得!ウガンダ代表は8カ国中7位という結果でしたが、会場の熱気と応援の盛り上がりは誰にも負けていませんでした。
週末には友達とテニスをしたり、家に遊びに行ったりしています。先日は「Rugby Africa Cup 2025」の決勝戦を観戦し、ジンバブエ対ナミビアの白熱した試合を楽しみました。ジンバブエが優勝し、2027年のラグビーワールドカップ出場権を獲得!ウガンダ代表は8カ国中7位という結果でしたが、会場の熱気と応援の盛り上がりは誰にも負けていませんでした。 文化的な違いも楽しみのひとつです。街を歩いていると「ムズング!(外国人)」と声をかけられることは日常茶飯事。初めは戸惑いましたが、今では笑顔で応える余裕もできました。
文化的な違いも楽しみのひとつです。街を歩いていると「ムズング!(外国人)」と声をかけられることは日常茶飯事。初めは戸惑いましたが、今では笑顔で応える余裕もできました。




